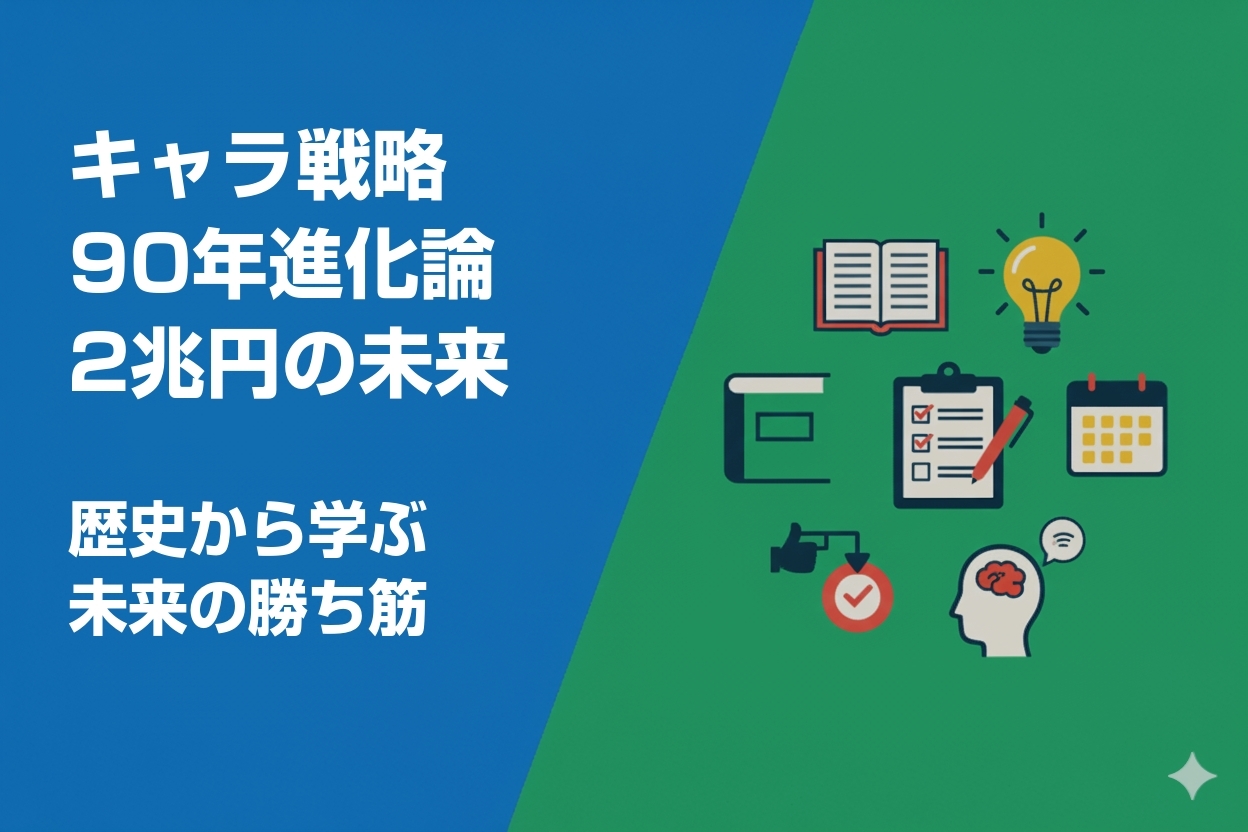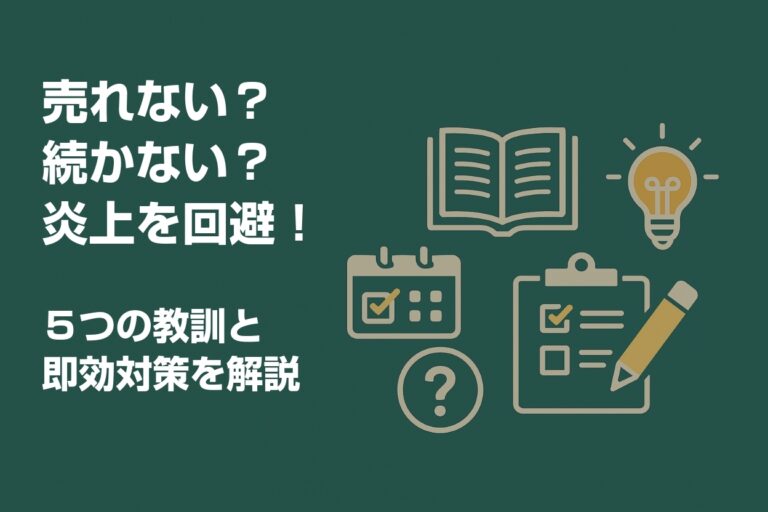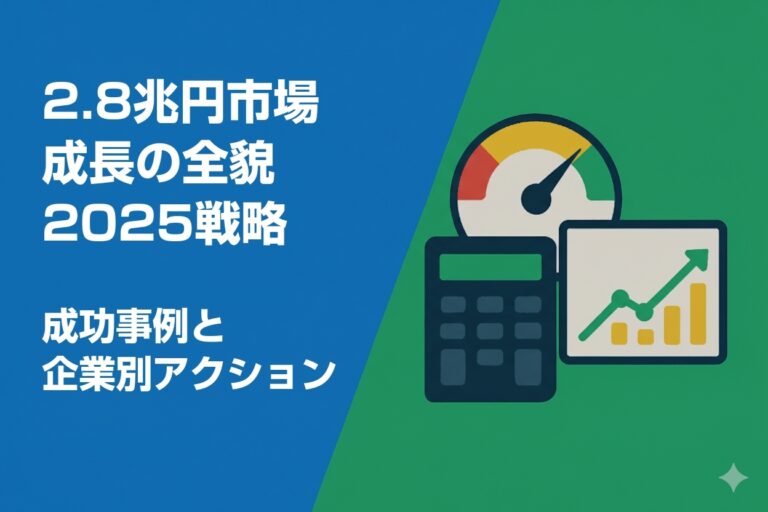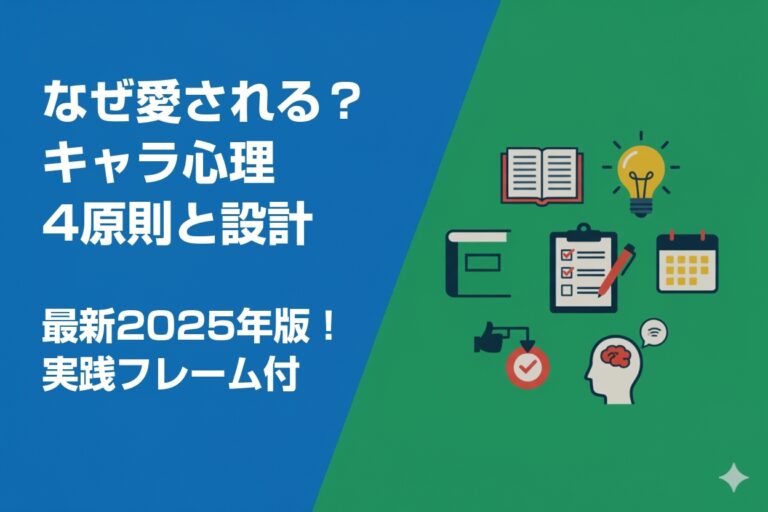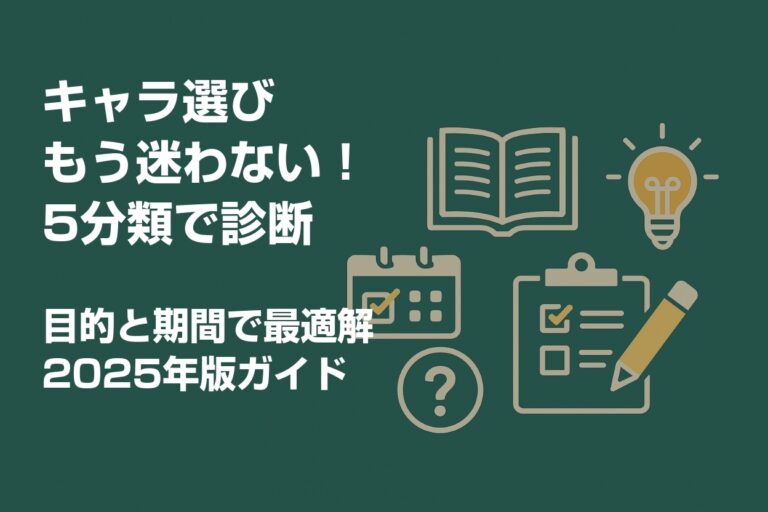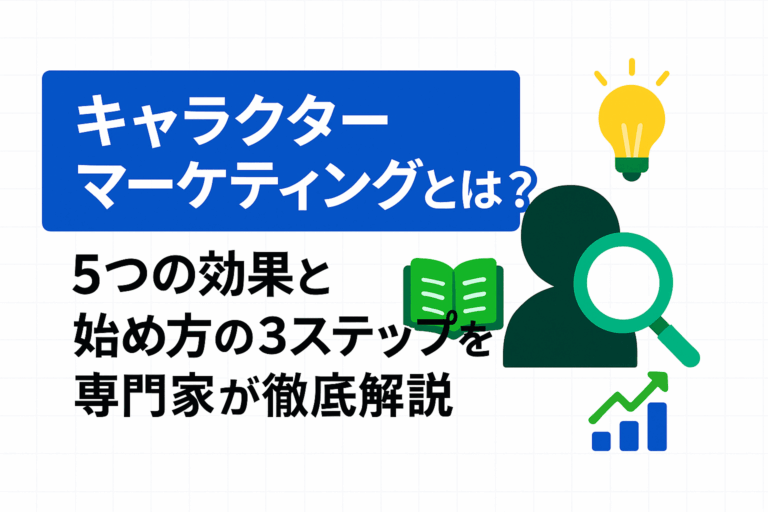企業キャラクターがここまで市場に浸透するとは、30年前には想像できませんでした。
2024年度の国内キャラクタービジネス市場は約2兆7,773億円に達し、その内訳を見ると興味深い事実が浮かび上がります。商品化権による収益が市場の大きな部分を占め、企業マーケティングにおけるキャラクター活用が主流になっているのです(参考:矢野経済研究所「キャラクタービジネスに関する調査を実施(2025年)」|2025|2024年度の市場規模は2兆7,773億円と推計)。
この19年間、WEBマーケティングの現場でさまざまな企業のブランディングを支援してきましたが、「キャラクターを作るべきか」という相談は年々増えています。ただ、多くの担当者が抱える悩みは共通しています。「いつ、どのような形で始めるべきか」「今はどんな手法が効果的なのか」——不確実性の中で、正しい判断を下すのは簡単ではありません。
当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間キャラクタービジネスに携わってきた専門家の知見をもとに、この分野の歴史と現在地を整理してきました。90年にわたる変遷を追うと、キャラクターマーケティングが「なぜ」「どのように」進化してきたのか、そして2025年以降に何が求められるのかが見えてきます。
本記事では、1930年代の黎明期から2025年の最新トレンドまで、時代ごとのエポックとなる出来事を一次情報で整理し、自社の次の一手を判断できる実務的なフレームワークを提供します。歴史を学ぶことは過去を振り返ることではなく、未来への投資判断の精度を高めることだと考えています。この壮大な歴史の流れを、本記事では4つの時代に分けて詳しく解説していきます。
第1章:黎明期~テレビ全盛「マスコットの役割が定まる」
1-1 広告・販促における”人格化”の起点(1930–70年代)
キャラクターマーケティングの起源を辿ると、1930年代のアメリカに行き着きます。
ケロッグ社が朝食用シリアルのパッケージにトニー・ザ・タイガーを起用したのは1951年でしたが、その前身となる動きは1930年代から始まっていました。当時の広告業界では、商品そのものを描くだけでなく、ディズニーやフライシャースタジオのアニメーションキャラクターに象徴され、商品広告に動きと情緒を加える手段も使われるようになり、後の広告キャラクター文化の礎を築いたと言われています。
日本では1960年代に入り、高度経済成長とテレビの普及が重なったことで、企業キャラクターの活用が本格化します。1965年、三洋電機が『ジャングル大帝』のキャラクターを起用したCMは、日本初の本格的なキャラクター広告として記録されています。この時期、テレビCM広告費は急成長を続け、1960年代には数百億円規模に達していました(参考:電通報「日本の広告費」の歴史から読み解く。」|2023|1959年には238億円)。
ここで重要なのは、キャラクターに求められた役割です。当時の広告では、商品の機能を伝えるだけでなく、「この商品を使う人はどんな価値観を持っているのか」を視覚的に表現する必要がありました。ブランディングの基本原則として、ブランドとは顧客への「価値の約束」であり、その約束を体現する存在としてキャラクターが機能し始めたのです。
ブランディングの基本原則として、ブランドとは顧客への「価値の約束」であり、その約束を体現する存在としてキャラクターが機能し始めたのです。
実務的に考えると、この時代の教訓は今も有効です。キャラクターは単なる装飾ではなく、顧客に対する約束を「人格化」する装置として機能します。
1-2 テレビCMと店頭での定着(1980–90年代)
1980年代に入ると、キャラクターマーケティングは「ビジネスモデル」として確立されていきます。
サンリオが1974年に発表したハローキティは、1980年代に国内外で爆発的な人気を獲得しました。注目すべきは、キャラクター単体ではなく、商品化権ビジネスとしてのエコシステムが構築されたことです。1970年代から著作権・商品化権の管理組織が整備され始め、1980年代にはキャラクター関連商品の市場規模拡大しました(参考:科学技術情報発信・流通総合システ「日本の広告史とキャラクター起用の変アニメーション産業における 1960 年代後半という時代」|2022|1966年には東映動画社内に版権課が設置され、商品化権許諾の体制が公式に整備される)。
この時期、企業は独自キャラクターの開発に本格投資を始めます。不二家のペコちゃん(1950年登場だが80年代に再定義)、明治のカール坊や、森永製菓のエンゼルなど、今も愛される企業キャラクターの多くがこの時代に戦略的に位置づけられました。
テレビCMでは15秒・30秒という限られた時間で記憶に残る必要がありました。キャラクターは、複雑なブランドメッセージを瞬時に伝達する「圧縮装置」として機能しました。これは現代のSNSマーケティングにも通じる原理です。
➡️ キャラクターの種類と分類をさらに詳しく知りたい方は、マスコット・IP・ゆるキャラの違いは?5大分類と診断フローで決める最適キャラ選び【2025年版】をご覧ください。
第2章:00年代の拡張「ご当地キャラ/企業キャラの二極化」
2-1 ご当地キャラ現象の広がり(自治体・地域振興)
2000年代に入り、キャラクターマーケティングは新たな局面を迎えます。
2002年、彦根市が彦根城築城400年祭のマスコットとして「ひこにゃん」を発表しました。当初は期間限定の企画でしたが、予想を超える反響を呼び、大きな観光資源となりました。さらに2011年に登場した熊本県の「くまモン」は、関連商品の年間売上が2023年には1,664億円を記録し、現在までの累計経済効果は1兆円を超えると試算されるなど、地域振興の成功モデルとして全国に波及しました(参考:熊本県「くまモン関連資料集」|2024|累計1兆円以上の経済波及効果と過去の年間関連商品売上実績)。
この現象が示したのは、キャラクターが持つ「共感を生み出す力」でした。ご当地キャラは地域への愛着を視覚化し、住民と観光客をつなぐ存在として機能しました。
ブランディングの観点から見ると、これはブランドステートメントの実践例です。ブランドには二層構造があり、表層の「約束」と深層の「原則」が一致している必要があります。くまモンの場合、「熊本の魅力を全国に伝える」という約束と、「県民と一緒に熊本を盛り上げる」という原則が整合していました。
実務的には、この時代の教訓は明確です。キャラクターは単独で機能するのではなく、そのキャラクターが体現する理念に共感する人々のコミュニティを形成して初めて価値を発揮します。
2-2 企業マスコットのブランディング装置化
一方、企業領域では、キャラクターが「ブランディング装置」として戦略的に位置づけられるようになります。
2000年代、多くの企業が顧客との情緒的なつながりを重視し始めました。機能的な価値だけでは差別化が難しくなり、情緒的な価値——つまり「このブランドを選ぶと、どんな気持ちになれるか」——が競争の軸になったのです。
SoftBankの「お父さん犬」(2007年)やau「三太郎」シリーズ(2015年開始だが企画は00年代後半)など、キャラクターを通じてブランドの世界観を表現する手法が主流になりました。これらのキャラクターは商品説明をするのではなく、「このブランドがいる世界」を視覚化しました。
ブランド理論で言えば、ブランドの使命は「選ばれ続けること」であり、そのためには同じ価値を繰り返し提供し続ける必要があります。キャラクターは、この「一貫性」を担保する存在として機能しました。
➡️ 市場規模と経済効果の詳細は、【2025年版】キャラクタービジネス市場規模2.8兆円の全貌|成長戦略と成功事例、企業別アクションまで徹底解説で深掘りしています。
第3章:10年代の転換「SNS・UGC・VTuberの台頭」
3-1 SNSでの会話のハブ化(UGC・二次創作・炎上学習)
2010年代、キャラクターマーケティングは根本的な変化を遂げます。
TwitterやInstagramの普及により、キャラクターは企業が一方的に発信するものから、ユーザーと「会話」するものへと変わりました。シャープ公式アカウントの「シャープさん」(2012年開始)は、企業キャラクターが人格を持ち、ユーザーと日常的にやり取りする先駆けとなりました。
この時期の重要な変化は、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の爆発的増加です。ファンが自発的にキャラクターのイラストや動画を制作し、SNSで共有する現象が日常化しました。キャラクターを活用したSNSマーケティングは、ブランド好意度を大幅に向上させ、エンゲージメント率は企業平均の2倍以上に達するケースも報告されています
ブランディングの観点から見ると、これは統合コミュニケーション(IMC)の実践です。IMCとは、複数の接点で一貫したメッセージを発信する考え方ですが、SNS時代には「企業が発信する一貫性」だけでなく、「ファンが語る一貫性」も重要になりました。
実務的には、この時代から「炎上リスク」も顕在化しました。キャラクターの発言や行動が不適切だと判断されると、瞬時に拡散され、ブランドイメージが毀損するケースが相次ぎました。これは次章で詳述します。
3-2 VTuber/バーチャルインフルエンサーの企業活用
2016年、キズナアイがYouTubeで活動を開始し、「バーチャルYouTuber(VTuber)」という新しいキャラクター形態が誕生しました。
VTuber市場は急速に拡大し、2024年度には国内市場規模が1,050億円に達すると予測されています(参考:矢野経済研究所「VTuber市場に関する調査(2025年)」|2025|2024年度の市場規模は1,050億円、2025年度は1,260億円に成長と予測)。企業は自社のVTuberを開発し、商品プロモーションやブランディングに活用し始めました。
VTuberの特徴は、従来のキャラクターにはなかった「リアルタイム性」と「インタラクティブ性」です。ライブ配信を通じて視聴者と直接対話し、その場で関係性を構築できます。これは従来の一方向的なキャラクターマーケティングとは本質的に異なります。
さらに、バーチャルインフルエンサー——3DCGで作られた架空の人物がSNSで活動するケース——も登場しました。米国のLil Miquela(2016年登場)は200万人以上のフォロワーを獲得し、ファッションブランドとコラボレーションを行いました。
このようにキャラクターの活躍の場は多岐にわたりますが、成功の鍵は各チャネルの特性を理解し、最適なコミュニケーションを行うことです。以下の表は、主要なSNSやメディアごとに求められる役割とKPIをまとめたものです。
第4章:20年代の現在地「データ×AI×安全運用」
4-1 データドリブン運用と測定の高度化(ROI設計)
2020年代に入り、キャラクターマーケティングは「データで管理する時代」に入りました。
従来、キャラクターの効果測定は曖昧でした。「認知度が上がった気がする」「ファンが増えた気がする」という感覚的な評価に留まるケースが多かったのです。しかし現在では、デジタルツールの進化により、詳細なデータ取得が可能になりました。
効果測定の枠組みとして、二軸四象限評価法が実務的に有効です。これは「見える/見えない」×「経済的/消費者的」の軸で指標を分類する方法です:
- 見える×経済的: 売上増加率、新規顧客獲得コスト削減率
- 見えない×経済的: ブランド価値向上による価格プレミアム
- 見える×消費者的: SNSエンゲージメント率、NPS(推奨意向)
- 見えない×消費者的: ブランド好意度、情緒的なつながり
実務では、これら4領域すべてに指標を設定し、バランスよく評価することが重要です。短期的な売上だけでなく、長期的なブランド資産の構築を測定します。
4-2 生成AI・3D・ARの実務導入(制作/運用/リスク)
2024年、生成AIの実用化はキャラクターマーケティングにも大きな影響を与えています。
実務的には、AIは「補助ツール」として活用し、最終的な判断は人間が行うハイブリッドアプローチが推奨されます。
4-3 ルール&権利(著作権・商標・ガイドラインの整備)
キャラクターマーケティングの拡大に伴い、法的リスク管理の重要性も増しています。
2024年現在、企業がキャラクターを展開する際には、以下の権利管理が必須です:
- 著作権: キャラクターのデザイン、ストーリー、名前などの創作物としての保護
- 商標権: キャラクター名やロゴの商業利用を保護
- 意匠権: キャラクターの立体的なデザインを保護
さらに、社内外のガイドライン整備も重要です。特にSNS運用では、キャラクターの「中の人」が不適切な発言をするリスクがあります。多くの企業が、以下のような運用ルールを設けています。
SNS運用ルール例
- 政治的・宗教的発言の禁止
- 他社や個人への批判禁止
- 炎上時の初動対応フロー
- 定期的な運用担当者研修
実務的には、キャラクター展開前に弁護士・弁理士に相談し、権利を確実に押さえることが推奨されます。初期投資を惜しむと、後で大きなトラブルに発展する可能性があります。
➡️ ROI測定の詳細な手法は、キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で実践的に解説しています。また、炎上対策の詳細は、キャラクター炎上対策の決定版|予防から初動対応、鎮火後までプロが教える【実践ツール付】をご覧ください。
第5章:【2025年版】事業戦略に活かす最新トレンドと意思決定フレーム
5-1 トレンド5選(2025年に押さえるべき潮流)
2025年現在、キャラクターマーケティングには5つの明確なトレンドがあります。これらは単なる流行ではなく、今後数年間の標準になると考えられます。
- 自社保有キャラクターの再評価
ライセンス料の高騰と、ブランドコントロールの重要性から、自社でキャラクターを保有する動きが加速しています。ライセンス契約の場合、年間数百万円から数千万円のコストがかかる上、キャラクターの使用方法に制約があります。長期的に見れば、自社開発の方がROIが高いケースが増えています。 - B2Bキャラクターの普及
従来、キャラクターはBtoC向けと考えられていましたが、B2B企業でも採用が進んでいます。セールスフォースの「アストロ」やSlackの「Slackbot」など、技術製品の親しみやすさを演出する事例が増えています。複雑なサービスを分かりやすく伝える「翻訳装置」として機能しています。 - ミニIPの多拠点運用
大規模なキャラクター展開ではなく、特定のコミュニティ向けに小規模なキャラクター(ミニIP)を複数運用する手法です。すべての顧客に同じキャラクターを押し付けるのではなく、セグメントごとに最適なキャラクターを用意することで、エンゲージメントを高めます。 - サステナビリティとの連動
環境問題や社会課題への関心が高まる中、キャラクターを通じてサステナビリティメッセージを発信する企業が増えています。電通の2024年の調査では、生活者の8割以上が企業のサステナビリティ活動を重視しています。このデータから専門家として言えるのは、キャラクターは単なる”広報担当”ではなく、企業の”倫理観の体現者”としての役割が求められているということです。抽象的なSDGsの目標を、キャラクターの具体的な物語や行動に変換することで、生活者の深い共感を獲得し、本質的な企業ブランディングに繋がるのです。
- メタバース・Web3への展開
バーチャル空間でのキャラクター体験やNFT化など、新しい価値創造の場が広がっています。ただし、技術先行ではなく、顧客体験の向上が目的であるべきです。
5-2 キャラクター戦略の3つの選択肢:保有・共同開発・ライセンス
自社でキャラクター戦略を始めるにあたり、大きく分けて「自社保有(オリジナル開発)」「共同開発」「ライセンス契約」の3つの選択肢が存在します。それぞれの特徴をコスト、スピード、リスクの観点から比較してみましょう。
【比較表】キャラクター戦略3つの選択肢(保有・共同開発・ライセンス)
| 項目 | 自社保有(オリジナル開発) | 共同開発 | ライセンス契約 |
|---|---|---|---|
| コスト | 高 (初期300万~) | 中 (100万~300万) | 低~中 (年50万~) |
| 開発スピード | 遅 (6~12ヶ月) | 中 (3~6ヶ月) | 速 (1~3ヶ月) |
| コントロール権 | 完全 | 共同 (調整が必要) | 制約あり |
| 主なリスク | 育成失敗、初期投資の回収 | 権利関係の複雑化、意見の不一致 | 契約終了、ブランドイメージの不一致 |
| 適した目的 | 長期的なブランド資産構築 | 地域連携、特定プロジェクト | 短期キャンペーン、市場テスト |
それぞれの選択肢にメリット・デメリットがあり、自社の事業フェーズや目的によって最適な方法は異なります。上の比較表と、以下の簡単な質問に答えることで、自社の進むべき方向が明確になります。この思考プロセスをフローチャートにまとめました。
- 時間軸: 3年以上の長期運用を想定しているか?
– YES → 自社保有を検討
– NO → ライセンス - 予算: 初期投資に300万円以上かけられるか?
– YES → 自社保有または共同開発
– NO → ライセンスまたは共同開発 - コントロール: キャラクターの使い方を完全にコントロールしたいか?
– YES → 自社保有
– NO → ライセンス - リスク許容度: 育成に失敗するリスクを取れるか?
– YES → 自社保有
– NO → ライセンス(既存人気を活用)
このフローチャートはあくまで基本的な判断軸です。実際には複数の選択肢を組み合わせる戦略も有効です。実務では、多くの企業が「段階的アプローチ」を取っています。まずライセンスで短期キャンペーンを試し、効果を確認してから自社保有に移行する方法です。
5-3 導入判断:Go/No-Go判定チェックリスト
そもそもキャラクターマーケティングを導入すべきか、客観的に判断するためのチェックリストです。
【戦略的整合性(5項目)】
- ブランドの人格化が必要か?(複雑なサービス、情緒的価値が重要など)
- 3年以上の長期的な視点で運用する覚悟があるか?
- 顧客との継続的な関係構築が経営課題か?
- 差別化が難しく、価格競争に陥りがちか?
- ターゲット顧客に響く明確なブランドストーリーがあるか?
【リソース確保(4項目)】
- 初期投資(最低50万円以上)の予算を確保できるか?
- 専任または兼任の運用担当者をアサインできるか?
- SNSやイベントなど、キャラクターを継続的に露出させる場があるか?
- 経営層がキャラクターの価値を理解し、支援する姿勢があるか?
【リスク許容度(3項目)】
- 炎上発生時の対応フローを事前に構築できるか?
- 育成に失敗する(期待した効果が出ない)リスクを受け入れられるか?
- キャラクターの一貫性を保つためのガイドラインを整備・運用できるか?
<判定>
Yesが9個以上: Go! 自社保有も視野に、本格的な導入を検討しましょう。
Yesが6〜8個: まずはライセンス活用から。 小規模なテストマーケティングで効果を検証しましょう。
Yesが5個以下: 時期尚早。 まずは目的を再設定し、リソース確保の計画を立てましょう。
【深掘りコラム】なぜ、多くのキャラクターは”忘れ去られる”のか?
90年の歴史は、成功事例だけでなく無数の”忘れられた”キャラクターの上に成り立っています。その多くに共通するのは「一貫性の欠如」と「コミュニティの不在」です。担当者の交代で性格が変わり、短期的なキャンペーンで使い捨てられ、ファンが語り合う場も与えられない。キャラクターは作るだけでは生命を宿しません。ブランドとしての一貫した哲学を背負わせ、ファンが愛情を注ぎ、育てられる「余白」を用意すること。これこそが、一過性のマスコットで終わるか、100年愛されるブランド資産になるかの分水嶺なのです。歴史から学ぶべきは、成功の法則だけでなく、失敗の構造でもあります。
➡️ 基礎から学びたい方は、キャラクターマーケティングとは?5つの効果と始め方の3ステップを専門家が徹底解説から始めることをお勧めします。また、実践的な活用方法は、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで詳しく解説しています。
まとめ
キャラクターマーケティングの90年の歴史を振り返ると、明確なパターンが見えてきます。本記事で解説した90年の歴史は、キャラクターの役割が「認知装置」から「経済エンジン」、そして「関係資本」を経て、現代の「最適化資産」へと進化するプロセスとして整理できます。
- 認知装置(1930-80年代): マスメディアで商品を人格化し、覚えてもらう段階。
- 経済エンジン(1990-2000年代): ライセンスビジネスや地域振興で直接的な経済価値を生む段階。
- 関係資本(2010年代): SNSでファンと対話し、コミュニティ(無形資産)を形成する段階。
- 最適化資産(2020年代〜): データで効果を測定・改善し、ブランド資産として管理する段階。
自社が今どの段階を目指しているのかをこのモデルに当てはめることで、取るべき戦略がより明確になるでしょう。
そして2025年現在、キャラクターマーケティングは「顧客との継続的な関係を構築する装置」として再定義されています。
次の一手を決める3つの質問
- なぜやるのか: 認知? エンゲージメント? 差別化?
- どう始めるか: 自社保有? 共同? ライセンス?
- どう測るのか: 見える指標と見えない指標のバランス
歴史から学べる最大の教訓は、「一貫性」です。キャラクターは一時的な施策ではなく、長期的なブランド資産として育てるものです。その覚悟があるかどうかが、成功と失敗を分けます。
キャラクターマーケティングは、もはや「やるかやらないか」ではなく、「どうやるか」の時代に入っています。この記事が、あなたの次の一手を決める一助になれば幸いです。
よくある質問(FAQ)
Q1: 企業キャラクターの歴史はいつから始まったのですか?
A: 企業キャラクターの起源は1930年代のアメリカまで遡ります。商品の擬人化表現が広告で使われ始めたのがこの時期です。日本では1960年代、テレビCMの普及とともに本格化しました。1965年の三洋電機『ジャングル大帝』CM起用が日本初の本格的なキャラクター広告として記録されています。
Q2: ご当地キャラと企業キャラの違いは何ですか?
A: 主な違いは「目的」と「収益構造」です。ご当地キャラは地域振興・観光促進が目的で、自治体が主体となり、経済効果は地域全体に波及します。一方、企業キャラは自社ブランドの認知向上・差別化が目的で、収益は企業に帰属します。ただし、運用方法(SNS活用、イベント展開など)には共通点も多くあります。
Q3: VTuberは”キャラクターマーケティング”に含まれますか?
A: はい、含まれます。VTuberは「リアルタイムで動き、視聴者と対話するキャラクター」として、従来のキャラクターマーケティングの進化形と言えます。ただし、従来の静的なキャラクターとは異なり、配信者の個性に依存する部分が大きく、コントロールの難易度が高いという特徴があります。企業が自社VTuberを運用する場合、「中の人」の教育とガイドライン整備が特に重要です。
Q4: 生成AIを活用したキャラクター制作のリスクは何ですか?
A: 主なリスクは3つです。1) 著作権の不明確性: AI学習データに既存キャラクターが含まれている可能性があり、権利侵害リスクがあります。2) ブランドコントロールの難しさ: 生成結果が予測しにくく、ブランドイメージと合わない出力がされる可能性があります。3) 倫理的懸念: 特定の人物や文化の無断使用と受け取られるリスクがあります。実務的には、AIは補助ツールとして活用し、最終判断は人間が行うハイブリッドアプローチが推奨されます。
Q5: キャラクターマーケティングのROIはどうやって出すのですか?
A: ROI測定には二軸四象限評価法が有効です。「見える/見えない」×「経済的/消費者的」の軸で指標を設定します。具体的には:
- 見える×経済的: 売上増加率、新規顧客獲得コスト削減率
- 見えない×経済的: ブランド価値向上による価格プレミアム
- 見える×消費者的: SNSエンゲージメント率、NPS(推奨意向)
- 見えない×消費者的: ブランド好意度、情緒的なつながり
すべての象限に指標を設定し、バランスよく評価することが重要です。詳細な測定手法はキャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で解説しています。
執筆者情報
WEBマーケティング会社経営19年目。中小企業のブランディング支援を専門とし、当編集部では世界的エンタメ企業で35年間キャラクタービジネスに携わった専門家の知見をもとに、実務に即した情報を発信しています。